![]()
 |
カリブ・ラテンアメリカ 音の地図/東琢磨編/音楽之友社 2002年発行。「カリブとラテンアメリカ全域の音楽の入門書を目指し、広範な地域的空間や質的に多様な音楽文化への関心を喚起し、その基本的な知識(音楽ジャンル、固有名詞などの事項)を得られることをまず第一に配慮した」(『総論に代えて』より) ブラジルに関しては、ポピュラーミュージックとしてサンバ、ボサノヴァについて、またローカルミュージックとしてノルデスチの音楽やバイーアのカルナヴァル、セルタネージャなどに言及している。 |
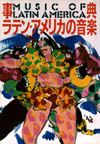 |
|
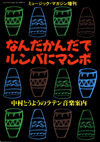 |
なんだかんだでルンバにマンボ 中村とうようのラテン音楽案内/ミュージック・マガジン 月刊『ミュージック・マガジン』の増刊として1992年に発行された。ブラジルに関してはエスコーラをはじめ、裏山のサンバ、バイーアとノルデスチの音楽など、多彩で奥行きの深いブラジル音楽の世界が描かれている。 |
 |
ラテン音楽パラダイス/竹村淳著/日本放送出版協会 ラテンアメリカをフィールドとする音楽ジャーナリスト、竹村淳さんのラテン音楽との出会いを描いたエッセイや、ラテンアメリカ諸国の音楽データ、CDガイドで構成されている。ブラジルの項では、エリゼッチ・カルドーゾを柱に、ショーロからサンバ、ボサノヴァ、MPBまで、“伝統と多様さを誇る南米最大の国の音楽”(本書より)の魅力を紹介している。1992年発行。2003年、講談社より文庫化された。 |
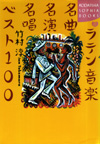 |
ラテン音楽 名曲名演名唱ベスト100/竹村淳著/講談社 タイトル通り、ラテンアメリカ音楽の100曲を通してラテンアメリカの諸相を捉えた本。ブラジル関係では、『イパネマの娘』『想いあふれて』『カリニョーゾ』『褐色のサンバ』『詩人の涙』『ジュルベバの木』『カリオカの夜』『ビリンバウ』『あの人が来る夜』『沈黙のバラ』『白い翼』の11曲がピックアップされている。1999年発行。 |
 |
バイーア・ブラック〜ブラジルの中のアフリカを探して〜 板垣真理子著/トラベルジャーナル 写真家・エッセイストの板垣真理子さんが、“ブラジルの中のアフリカを探して”、サルバドールやレシーフェを旅する。カーニバル、ブロコ・アフロ、カルリーニョス・ブラウン、カンドンブレ、ボンフィンの祭り、ストリート・チルドレン…。これまでに何度もアフリカを訪れている彼女のバイーアを見つめる眼差しは鋭くも温かい。1997年発行。 |
 |
カーニバル・イン・ブラック〜ブラジルに渡ったアフリカの神々と祭り〜 板垣真理子著/三五館 『バイーア・ブラック』の姉妹本。『バイーア・ブラック』がエッセイ集なのに対して、こちらは写真が中心なので、バイーアの魅力が臨場感いっぱいに伝わってくる。「バイーアでアフリカを探す時、多くのものにヨルバを発見する」「ヨルバとは西アフリカ、現在のナイジェリア西部からベニン共和国にかけて居住する人々の呼称である」(本書より)。1997年発行。 |
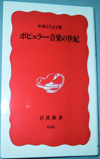 |
ポピュラー音楽の世紀/中村とうよう著/岩波新書 ぼくはこの世紀を“ポピュラー音楽の時代”としてとらえてみた。ポピュラー音楽こそ時代に生きてきた大衆の心を写す鏡だったのであり、これを見つめることで歴史の基底が明らかになると思うからだ。(「まえがき」より) |
 |
|
 |
別冊
MUSIC MAGAZINE ブラジル音楽なんでも百科/ニューミュージック・マガジン社 『ミュージック・マガジン』の別冊として1981年に発行された。当時はタイトル通り、これ1冊あればOKであった。執筆陣は中村とうよう、濱田滋郎、大島守、竹村淳、森本タケル、高場将美ら蒼々たるメンバーを揃えている。浅田英了のグラビアも素晴らしい。私はこの本で、パンデイロの叩き方や、カヴァキーニョのチューニングなども知った。今読み返して時代を感じるのは『10人のスーパースター』というコーナー。エリゼッチ・カルドーゾ、ベッチ・カルヴァーリョ、ジョアン・ノゲイラ、エルザ・ソアーレス、マルチーニョ・ダ・ヴィラ、レシ・ブランダン、ジョルジ・ベン、ジルベルト・ジル、マリア・ベターニア、ガル・コスタが選ばれている。(敬称略) |
 |
music gallery 11 サンバ〜バイーアからリオへ吹く風〜 浅田英了・高場将美・森本タケル著/音楽之友社 1985年発行。ブラジルにあふれんばかりの愛情を注いできた浅田英了の写真が、臨場感たっぷりに、“サンバ”の魅力を教えてくれる。全79ページと薄い本だが、マンゲイラ、ポルテーラの訪問記やカルトーラ、ネルソン・カヴァキーニョとの交流記(浅田)、歴史をふまえながらブラジル音楽を俯瞰する高場将美のエッセイ「ブラジル音楽の多様さを支えるもの」、森本タケルの「MPB STAR GALLERY」「ブラジル音楽MPB必聴盤30」など、中味は盛りだくさん。(敬称略) |
 |
旅の指さし会話帳 [23] ブラジル/猪木亜弥子ファニー著/情報センター出版局 「言葉には自信ないけど、ブラジルへ行ってみたい」という方々におすすめなのが、A5サイズ全128ページのこの本。2002年11月から2ヶ月間、サンパウロに滞在した私も常に持ち歩いていた。ジャンルやシチュエーション別に構成されたページには、ふんだんにイラストが盛り込まれているので、とても便利。簡単な辞書機能も付いているので、これ1冊あればなんとかなる(はず)。 |
 |
ブラジルを知るための55章/アンジェロ・イシ著/明石書店 2001年発行。ブラジル、およびブラジル人の最大の魅力は多様性。サンパウロ出身の日系人著者が、ブラジルの真の姿を日本人に理解してもらおうと、この国を様々な角度から描いたのが、この本である。『イパネマの娘』誕生の真実やカーニバルの「神話崩し」など、音楽に関する記述はわずかだが、この国の現状を理解するために、ブラジル音楽ファンにもぜひ読んでいただきたい。 |
 |
|
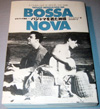 |
ボサノヴァの歴史 外伝〜パジャマを着た神様〜 ルイ・カストロ著/国安真奈訳/音楽之友社 上記『ボサノヴァの歴史』の続編。副題の「パジャマを着た神様」とは、いうまでもなくジョアン・ジルベルトのことだ。このタイトルが暗示しているように、本書では新たに発掘されたミュージシャンにまつわるエピソードや、90年代以降のボサノヴァを取り巻く環境について記されている。 |
 |
ブラジリアン・ミュージック/中原仁編/音楽之友社 1995年の刊行以来、重版が続くブラジル音楽ガイドの決定版。これ1冊でMPB、バイーア、サンバ、ボサノーヴァ、ショーロ、ノルデスチなど多彩なブラジル音楽を俯瞰できる。「音楽ファンのためのリオ・ガイド」が添えられているのも、うれしい。 |
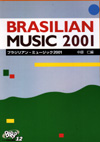 |
2001年発行。「ブラジリアン・ミュージック」の続編となるのが本書である。「ブラジリアン・ミュージック」はブラジル音楽全般をガイドしているのに対し、この本では現代の視点からボサノヴァ以降のブラジル音楽をより広く多面的に取り上げている。音楽ファンのためのブラジル旅行ガイドも、リオに加えて新たにサンパウロも設けられており、より充実した。 |
 |
|
 |
MUSIC MAGAZINE 増刊 トロピカリア・ブラジレイラ 高橋道彦監修/中原仁協力/ミュージック・マガジン 1999年発行。トロピカリズモ以来30年あまりのブラジル音楽の歩みを、トロピカリズモがまとっていたサウンド感覚を軸に俯瞰した本。したがって、「CDベスト100」にはロックやファンク的な感覚を含有した90年代のアルバムが数多くピックアップされている。あらためて、ブラジル音楽の豊潤さ、懐の深さに気付かされる。 |
 |
アントニオ・カルロス・ジョビン〜ボサノヴァを創った男〜 エレーナ・ジョビン著/国安真奈訳/青土社 ボサノヴァの「法王」、アントニオ・カルロス・ブラジレイロ・ヂ・アルメイダ・ジョビン(ジョビンのフルネーム)の伝記。彼の書いた楽曲が何故あれほど魅力的なのか、その答えがこの約400ページの本の中にある。実妹エレーナの深遠な愛が行間からあふれ出るすぐれた伝記作品だ。ディスコグラフィーや写真などの貴重な資料が豊富に収められているのもうれしい。また、意外な人選だが山下洋輔による「解説」は、音楽理論にも言及しており、興味深い。1998年発行。 |